
広告について。
サイト運営のため、Googleアドセンス
による広告があります。
Contents - 目次
ブルーライトカットとUVカット効果の体験談。
ブルーライト&UV。カット率90%超のオーバーグラス。
オーバーグラスのメリット。
既存のメガネの上からかけられるオーバーグラスは、安くて便利。
ブルーライトとUV(紫外線)がそれぞれ90%以上のカット率があるタイプは、確かに効果が感じられた。
オーバーグラスのデメリット。
メガネが二重になるため重い。長時間かけていると、鼻にメガネの跡が残ってしまう。
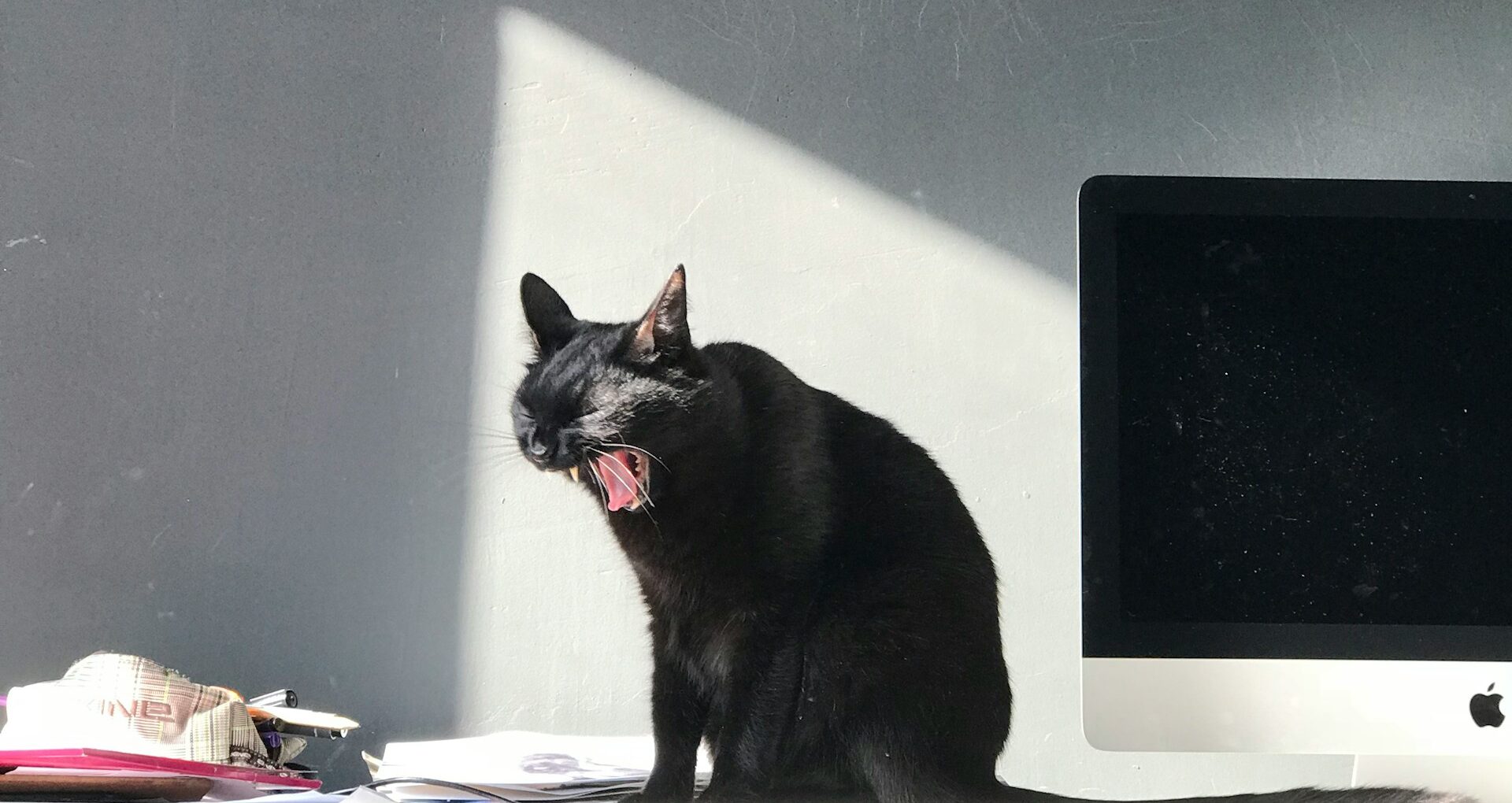
Photo by Valentin Vlasov
ブルーライトのみ。カット率60%のメガネ。
オーバーグラスから、通常のメガネへ買い替え。
オーバーグラスが壊れてしまったため、通常のメガネ、ブルーカットのみ60%カットのメガネに買い替え。
予算内では、それ以上のカット率や、ブルーライト&UVの両方がカットされたものは見当たらず。
メガネはネットと実店舗で確認。
ネットだけでなく、都心と地方都市の複数店舗で実際に見て探し、価格とデザインで決定。
スタッフの方の対応も良く、視力検査やテンプルなどの調整もしてもらえた。
(※既存のメガネやコンタクトの数値がわからない場合や、初めてのメガネ作成時などは、眼科の方が厳密。)
重さもなく、かけ心地も良い。
見える色が違う(黄色、暖色系となる)くらいで、とくに違和感はなかった。

Photo by Christian Wiediger
ブルーライトカットのみ、しばらくしてからの急転直下。
ところが、1週間から10日ほどしてから、急激に目に強い痛みを感じるようになった。
自分の場合は眼精疲労やドライアイ、VDT症候群やIT眼症などではなく、数年前から慢性疼痛症が再発していた状態。
羞明にも近いが、光に過敏、刺激に敏感という感覚ではなく、目の筋肉や神経の勤続疲労という感じ。
それ(持病)が、急に悪化。
結果的にさらに別のメガネを買うことになり、予算オーバーどころか2倍の出費に。
補足。
- 自分は体育会系育ちであり、小中高の12年間欠席は0だった。
- 眼科へは少なくても年に1、2度、定期的に通院しており、視力は変わっておらず、緑内障や白内障などの病気でもない。
- 最初の慢性疼痛症では腰痛で2度入院。その後にはいとこが線維筋痛症の診断を受けている。
- いとこはおしゃれで明るい性格。極めて厳しい状況だったようで、命を絶っている。
- 自分たちの祖父と祖母、おじとおばにあたる人物は、7人中5人がかなり若いうちに亡くなっている。生き残ったそれぞれの親である2人が成人するずっと前に。原因は不明。江戸時代やコロナ禍のころの出来事ではない。
- いとこ同士の遺伝子共有率は約12.5%。
- 遺伝子診断、DNA検査を行っている23andMe社によるデータでは、いとこ同士の遺伝子共有率は平均14.4%。範囲としては8%〜22%。
参照元:Average Percent DNA Shared Between Relatives – 23andMe Customer Care - 遺伝子が共通しても、必ず発現するというわけではない。
ブルーライトは自然光からの方が多く出ている。
スマホやパソコンよりも、太陽光の方が桁違いに多い。
ブルーライトは人間の目で見ることができる光(紫外線と赤外線の間の可視光線)のうち、最も波長の短い光。
そのブルーライトは、デジタル機器だけでなく、電球やLED、自然の太陽光からも出ており、むしろ太陽からの方がはるかに多い。
近年のイメージとは、ズレがある。

Photo by Catherine Heath
ブルーライトは、目の奥にある網膜まで届きやすい。
光は眼球の最前面にある角膜、そして虹彩、瞳孔から、水晶体、硝子体を通過し、奥にある網膜へ届く。
ブルーライト(青色光)は、可視光線の中で最も波長の短い光という特徴により、網膜まで届きやすい。
網膜は視神経とも繋がっており、光を電気信号に変えて脳に伝える。
(※網膜にある視細胞(桿体細胞や錐体細胞)が光を電気信号に変え、双極細胞などで整理され、網膜最深部の網膜神経節細胞や軸索の集まりの視神経を通じて脳へと伝達。)
ブルーライトが有害という誤解。
「ブルーライト = スマホ(パソコン) = 有害」というイメージは誤解。
ブルーライトは、デジタル機器から出る「特別な光」ではない。

Photo by Matheus Queiroz
ブルーライトカットメガネには意味がない?
米国眼科アカデミー(AAO)による発表。
ブルーライトをブロックしたメガネは価値があるのでしょうか?
米国眼科アカデミー(AAO)は2021年に、コンピューターの画面から発せられる光が目に有害であるという科学的証拠はないと発表している。
そのため米国眼科アカデミーは、ディスプレイ(モニター、画面)を見ての作業時に、ブルーライトカットなどの特別なメガネを推奨していない。
参照元:Are Blue Light-Blocking Glasses Worth It? – American Academy of Ophthalmology
アメリカ国立医学図書館による発表。
成人の視力、睡眠、黄斑の健康のためのブルーライトフィルター付きメガネレンズ。
2023年にもアメリカ国立医学図書館のサイト上でも、同様の臨床試験の結果の発表がされている。
睡眠の質に与える影響も、非常に確実性の低いエビデンスであり、不確定とのこと。
日本眼科医会による発表。
小児のブルーライトカット眼鏡装用に対する慎重意見。
これらはアメリカに限ったことではなく、2021年に日本の眼科医会からも、子どものブルーライトカットメガネへ対しての「慎重意見」が発表されている。
参考文献には前述の米国眼科アカデミーだけでなく、逆の見解も含まれている。

Photo by Tim Mossholder
ブルーライトの研究結果を基にした、米国眼科アカデミーの提案。
米国眼科アカデミーの提案。(2021年)
目の疲れを和らげる、米国眼科アカデミーのTips。
米国眼科アカデミーのサイト上では、Tipsとして下記の提案がされている。
- 画面から約25インチ (約63.5cm。腕の長さ。) 離れて座る。
- 「20-20-20」ルールでの休憩。20分ごとに、20フィート(約610cm)離れた物体を、20秒見る。
- 目薬でのリフレッシュ。
- 部屋の照明や、スクリーン(ディスプレイやモニター)の調整。
- コンタクトレンズよりもメガネの着用。
参照元:Are Blue Light-Blocking Glasses Worth It? – American Academy of Ophthalmology

Photo by Sylvie MEUNIER
ディスプレイ(スクリーン、モニター、画面)からの目の保護、アイケア。
画面のブルーライトからの目の保護や目薬の処方。
眼精疲労やVDT症候群などはかなり以前から。
米国眼科アカデミーのTipsのようなことは、ずっと以前から言われていた。
パソコンやスマホに限らず、テレビやゲームなどでも。
それが近年の研究結果でも効果的という、裏付けがされたことになる。
目薬については、眼科で処方してもらうと普通は保険適用がされるので、診察代も含め安価で質も良い。
画面との距離の目安。
40cm以上が目安。
眼科を含め一般的な目安としては、スマホやタブレットは、画面から40cm以上離すことが提案されている。
知名度の高い、市販の目薬の会社でも同様。
参考:VDT症候群の治療方法 | 参天製薬日本サイト
参考:VDT症候群 – HOYA株式会社
米国眼科アカデミーでは約25インチ。(約63.5cm。腕の長さ。)
日本人よりも平均身長が高いアメリカの、米国眼科アカデミーのサイト上では、画面から約25インチ (約63.5cm。腕の長さ。) 離れて座る、となっている。
参考:Are Blue Light-Blocking Glasses Worth It? – American Academy of Ophthalmology

Photo by Christin Hume
光を近くで見ると網膜が傷つく。
そもそも「光」を近い距離で見ると目が痛くなるのは当然であり、太陽を虫眼鏡を見てはいけないことは小学校でも習う。
家庭用の電球を至近距離で見てもかなりの刺激があり、自動車のハイビームも対向車側から見ると目がきつくなる。
ダークモードの効果について。
ダークモードの科学的根拠。
ダークモードも科学的根拠がないと言われることがある。
しかしこれは、白は光を反射し、黒は光を吸収するという、色の性質で説明ができる。
日常生活でも、日中と夜間では明らかに眩しさは違う。

Photo by Szabo Viktor
サングラスの効果。
太陽光への対処として長年「サングラス」が使用されており、サングラスには近年だけでも軽く100年以上の歴史がある。
日中よりも夜間の方が暗く、目への刺激も少ない。
日没後は自然界がダークモードのようになるので、理由がない限り、夜にサングラスはかける必要もない。

Photo by dilkhush lakhtia
アイブラックの効果。
野球やアメフトの選手による「アイブラック」にも80年以上の歴史があり、科学的な検証も行われている。ダークモードについては、それらが一定の根拠となるだろう。

青い目が多い欧米人に限らず、シアトル・マリナーズ時代の城島健司選手もアイブラックを取り入れていた。
Photo by アイブラック – Wikipedia
ディスプレイの「色」と「光」について。
色は、光の波長によって決まる。
青が一番短いことは確か。
スマホやパソコンからよりも、太陽からの方がずっと多く含まれている。
- 赤(Red):波長が長い(約620〜750nm)
- 緑(Green):波長が中くらい(約495〜570nm)
- 青(Blue):波長が短い(約450〜495nm)

Photo by Tyler Daviaux
特別な光ではなく、RGBで構成されている。
ディスプレイの色は、赤・緑・青の3色(RGB)の掛け合わせで、加法混色と呼ばれる。
白はマックスの赤255、緑255、青255となり、黒はミニマムの赤0、緑0、青0となる。
ライトモードは白背景がベースで、ダークモードは黒背景がベースとなるので、サングラスの有無や日中と夜間のように、目(網膜)に受ける光の量は大きく異なる。
ライトとダークで試してみるとわかる。
これは単純に、パソコン画面と目との間に、簡易的なフィルターとして新聞紙やA4用紙などをぶら下げてみるとわかる。
ナイトモードや明度や輝度での光の調整。
ディスプレイは調整が可能。
また、多くのディスプレイは手軽にナイトモードや明度の調整が可能。輝度の調整もできる。
オフィスや自宅などの照明と合わせることで、目への負担を減らせられる。

Photo by Nubelson Fernandes
照明も調整が可能。
昼間は外からの太陽光が入ってくるので、窓やカーテンなどで遮らない限り、室内も明るい。
そのときはディスプレイの光もそれほど気にならない。
夜間はそうではないので、昼間のカーテンのように、屋内での照明によっての明るさの調整ができる。
過度なコントラストは、目への負担要因にもなる。
室内とディスプレイの明るさには、統一感があった方が、目への負担も少なくなる。
テレビやストリーミング映像などで「フラッシュがあります。」というような注意喚起があるように。

Photo by Clay Banks
ディスプレイから離れることも効果的。
タイマーやポモドーロアプリの利用。
パソコンでもスマホでも、一定時間(作業時間25分につき休憩5分など)ごとに休憩の知らせを音や通知で行えるアプリも多々ある。
作業時間や休憩時間は、自分で設定することもできる。
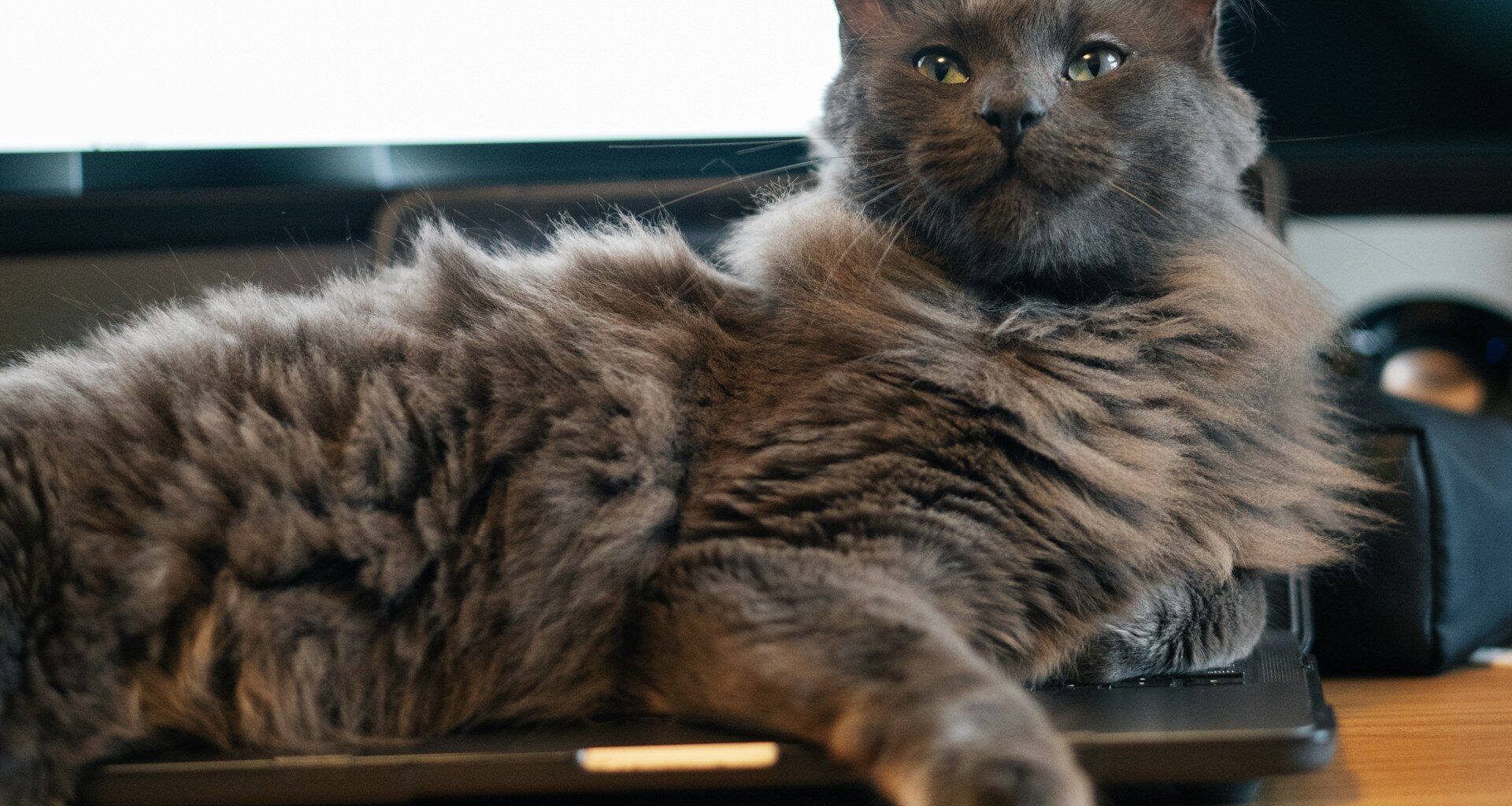
Photo by Maryam Tello
以上、参考になれば幸いです。
※Webデザインは実務数年、職業訓練校講師数年、フリーランス数年、計15年以上のキャリアがありますが、一気にがぁっと書いているので「です・ます調」ではありません。(元々はメモ書きでした。) ※事実や経験、調査や検証を基にしていますが、万一なにかしら不備・不足などがありましたらすみません。お知らせいただければ訂正いたします。 ※写真は主にUnsplashやPixabayのフリー素材を利用させていただいております。その他の写真や動画もフリー素材やパブリックドメイン、もしくは自前のものを使用しております。

